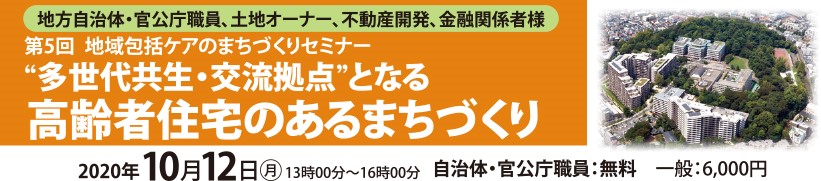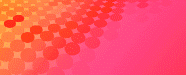---連載 点検介護保険---
次は、安楽死の議論を
「ACPってどういう風にやるの」「人生会議と言われてもどんな資格者が何回開けばいいの」。昨年3月に厚生労働省が公表した「ACP」について、医療や介護関係者の関心は高い。「ACPセミナー」ばやりでもある。
ACPとは、アドバンス・ケア・プランニングのこと。アドバンスは事前に、前もってという意味だから、厚労省は「人生の最終段階について、本人が家族等や医療・介護者たちと事前に繰り返し話し合うプロセス」と説明している。
このACPという言葉は、厚労省が公表した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の解説編の中で初めて登場した。そこでは、「諸外国で普及しつつあるACPの概念を盛り込み…」と記された。
つまり、ガイドラインとACPはほぼ同じことである。そして昨年11月には、ACPを「人生会議」と名付けて普及に力を入れだした。
昨年公表したガイドラインは、2007年作成の2度目の改訂版である。当初の名称は「人生の最終段階…」ではなく「終末期…」としていた。最初のガイドラインは、前年に起きた富山県射水市民病院の事件を契機に出された。同病院の医師が7人の終末期患者の人工呼吸器を外して逮捕され大騒動になったもので、結局、検察は不起訴処分にした。本人や家族が望んでいたことが分かったためで、終末期に対する国の姿勢が問われた。この事件が、ガイドラインを生み、ACPの登場を促して先進諸国に追いつくことになった。
ACPが注目されているのは、昨年4月の改定で医療保険と介護保険の中に報酬要件として盛り込まれたためでもある。訪問診療と訪問看護のターミナル報酬、地域包括ケア病棟の入院料と入院管理料、それに介護保険の訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護である。
それまでは「事前指示書」(リビング・ウィル)によって本人の意思表示がされていた。そこから、医療者や介護者にも話し合いの輪を広げ、さらに議論を繰り返せとした。意思決定範囲を拡大させることで、死がより身近になるのはいいことだ。
かなりの高齢者でも救急車を呼び、病院で延命治療を受けるのが当然の日本社会。他の先進諸国にはない日本独特の「常識」が変わる可能性が高い。自宅や自宅に近い環境の施設で、緩和ケアを中心にした道が開ければと思う。死の選択肢が増えていけば、次の課題は安楽死の議論だろう。
NHKが6月2日、スイスに行って安楽死を遂げた難病患者のルポ番組「彼女は安楽死を選んだ」を放映した。衝撃的な内容が大きな反響を呼んだ。医師が死をもたらす安楽死は日本ではまだ認められていない。
番組を見た京大名誉教授の佐伯啓思さんは、「何か妙に崇高な感動を覚えた」と朝日新聞で記した。続けて「安楽死にはかねて肯定的であった」とし、なぜなら「この先、死を待つだけの生が耐え難い苦痛に満ちたものでしかなければ、出来るだけ早くその苦痛から逃れたいからである」と選択肢の一つと説く。
NHKの番組では当の女性患者が「死の選択は、どのように生きるかと同じように重要なこと」と、死の間際に話していた。日本では得られない選択肢がスイスにはあった。
人生にできるだけ多くの選択肢があることは「幸せ」につながる。人間の歴史はその選択肢を広げるプロセスだろう。身分制を打破した市民革命ひとつとっても明らかだ。身近なところでは、就業先を変われない技能実習生は選択肢がない典型。成年後見制度は20年目にして後見人を変えることができるようになりつつある。
安楽死を推進する政党が参院選挙では比例代表で約27万票を集め、タブー視から踏み出した。人生の選択肢を増やすことに異論はないはずだ。

ジャーナリスト
元日本経済新聞
編集委員
浅川 澄一氏
1971年、慶応義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)





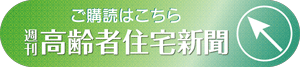

10.2-2-1.jpg)