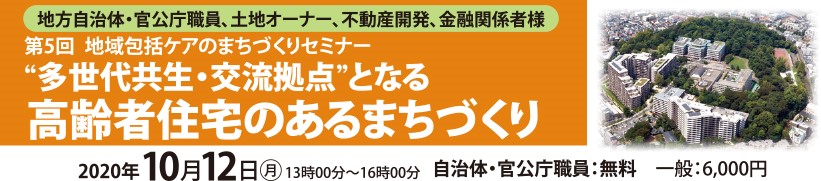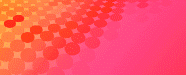死生学は死に直面した人とその家族のケアを考える学問として発達したが、日本では特に死と生をどう考え、向き合うかが中心テーマになっている。東京大学大学院の清水哲郎特任教授は医療・介護現場における「臨床倫理」および「臨床死生学」について研究を積み重ねている。延命治療や緩和ケア、医療者と患者・家族のコミュニケーションなどについて聞いた。
── 医療・介護現場における臨床倫理・死生学とは。
「医療・介護従事者が日々、患者・家族と応対しながら、ケアを進めていく際に、『どのようにコミュニケーションを進めて、治療やケアを選択していこうか』と、個別事例ごとに考える営みが臨床倫理。医療者は人間として、また医療者としての姿勢をとりつつ、本人・家族と共に途を進もうとする。そのような姿勢がそもそも〝倫理的〟なのである」
「死生学は1960年代後半から70年代初めに、死に直面している本人と家族のケアに関する学問として活発になった。痛み、不安、悲しみ、恐れなど死に直面したつらさに対して、本人や家族にどう向き合い、どのようにケアすべきかを考えていた」
── 延命治療、高齢者ケアでは特に胃ろうが議論されるようになった。
「口から食べられなくなって、胃ろうを選択する。命が長くなるなら胃ろうはすべきなのか。認知症が進んで、喜怒哀楽が表出されないような状態になっても、医療の世界では、死は敗北、忌むべきもの、できれば先延ばしにしたい、としてきたのではないか。臨床場面に関わる死生学は『生を保ち、死を先送りする』という価値観でよいのかを問う。それは臨床倫理が、個別のケースに即していたずらな延命は適切か、老いが進んで寝たきりになっても生命維持が本人の人生にとって最善か、といったことを検討する際の基礎となる」
── 〝いのち〟とQOLの関係についてはどう考えるか。
「いのちには生物学の対象になる生命という相と、いのちの物語りを創りつつ進む人生という相がある。身体的生命がなければ、人生は展開できない。人生が目的として価値の源と言える。QOLは人生についての評価。生命維持が見込める治療を行うかどうかの選択の際は、生命維持が見込めるかどうかだけではなく、延びた生命の中身について考える必要がある」
── 治療の現場での意思決定のあり方について、厚労省や諸学会からガイドラインが出るなど注目されている。
「ケアを提供する側からの一方的な説明になっているケースが多いと思う。医療を提供する側と受ける本人・家族側が、専門家として持っている情報と本人の人生に関する情報を互いに共有しつつ、コミュニケーションを通して合意を目指すのが望ましい。医療者が患者の人生について理解し、本人・家族と一緒に考えるという姿勢が重要」
── 自分の心積りを書き込める「心積りノート」については。
「高齢者が住み慣れた地域で最期まで自分らしく生きるために、心身の健康面から今後の人生を長期的に考える『心積りノート』を2015年に開発した」
「高齢期にさしかかっている方、少し衰えてきたと感じた方が、今後の人生を見通しつつ(〝上手に老い、最期まで自分らしく生きる〟ことを目指して)、老いの進み方に応じてどう暮らし、どのような活動をしようかと、また医療にかかる際にどういう治療なら受けようか、受けないでおこうかと心積りする場面を想定している。心積りしたことをメモしておき、考えが変わったら、書き直せるようにノートにした。(「記入編」と「考え方・書き方編」で構成されている)」
── 一般的なエンディングノートとの違いは。
「エンディングノートとの違いは、人生の最終段階の時期だけを考えるのではない点。元気なうちから私たちが生きていく経過を見通して、老いが進むにつれて、どこで誰と暮らすか、受けたい治療、やってほしいお世話が変わっていくことについて心積りをしておこうというのがこのノートの主旨。いわば〝終活〟ではなく、〝老活〟を支援するツールとして勧めている」
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)





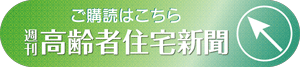

10.2-2-1.jpg)