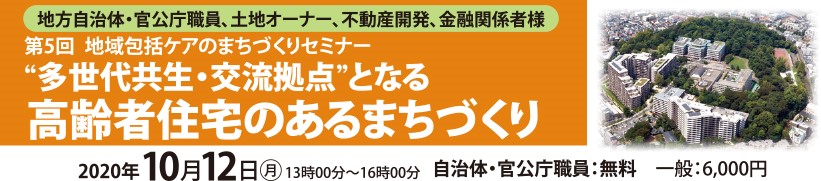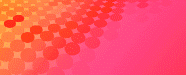医療者だけでなく、私たちが「死」にどのように関わるべきかが問われる事件が起きた。東京都福生市の公立福生病院での人工透析治療をめぐる「事件」だ。3月7日の毎日新聞朝刊が「医師、『死』の選択肢提示」「透析中止 患者死亡」「指針逸脱 都、立ち入り」という見出しで報じた。その日の夕刊と翌日朝刊で新聞各紙が同様の見出しで追随した。
いずれも、死につながる透析の中止を医師が患者に提示したことが悪い、という主張である。果たして、そうなのか。昨年3月、厚労省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を発表し、その解説編に「海外で普及しつつあるACPの概念を盛り込み」と記し、ACPの考え方を日本で広めようとしている。
ACPとは事前に医療やケアのプランを考えることである。本人を交えて、家族や医療とケアの専門職などが十分に話し合う。厚労省は昨年11月「人生会議」の日本語を当てた。終末期になる前から始めよ、ともいう。
この会議で、専門職は想定される治療法を含めてあらゆる対応策を提示しなければならない。その中には、「治療しない」「治療途中での中止」による緩和ケアへの選択肢、つまり自然死、尊厳死の道も含まれる。とことん延命治療を望む患者もいるだろう。いずれにしろ選択肢の中から決定するのは本人である。
福生病院の医師が「死の選択肢を提示」するのは当然で、むしろその選択肢を示さない方が専門職としての責任を問われるのではないだろうか。
ACPどおりに、患者本人の意思が貫かれて死を迎えたようだ。3月28日の共同記者会見で病院側は「患者が透析を拒否したため、透析をできなかった」(朝日新聞、産経新聞)と話している。さらに「病院から透析中止の選択肢を示していない」と病院医師は語り、各紙の第一報を否定してしまった。朝日は28日の紙面で、「(8日の記事は)東京都から聞いた」と取材源を明かし、病院からの確認が取れていなかったことを認めた。
ただ、病院の対応も配慮が足らなかったようでもある。ACPでは、関係者の話し合いを繰り返し行い、記録にとどめておくことが欠かせない。プロセスが重要なのだ。
だが、患者の夫は「医者は人の命を救う存在だ。『治療が嫌だ』と本人が言っても、本当にそうなのか何回も確認すべきだと思う」(3月7日毎日)と、病院の非を訴え、その手記を毎日新聞電子版で公表している。これに対し、病院は「遺族とのトラブルはなかった」(3月29日東京新聞)、「適切なプロセスを経た」(同日産経)と記者会見で主張した。
血液透析そのものも問われている。人工透析患者は2017年末で33万4505人。血液にたまる老廃物や余分な水分除去のために、4時間ほどじっと横たわりながら受ける。週3回必要で、止めると苦しみ、数週間内に亡くなるという。
費用は月約40万円だが、助成制度により患者負担は月1万円程度。医療機関には長期にわたる安定した「収入源」だ。
人工透析には、患者自身の腹膜を使って行う腹膜透析もあるが、長期間は難しく、1万人に達しない。実は根治できる理想的な治療法がある。腎移植だ。移植希望者は1万2100人に上るが、17年に実現できたのは1742人のみ。平均待機期間は4850日(13・3年)と長い。欧米では移植が主流だ。
臓器提供者があまりにも少ないのが日本。腎移植でも親族に限定される生体腎が9割近くで、他人の死後の臓器を活用する献腎は年200件に達しない。10年の臓器移植法改正で健康保険証や運転免許証、それにマイナンバーカードには「臓器提供の意思表示」の欄が設けられた。腎臓もその対象だ。「遺体にメスを入れたくない」より、「人の役に立つ」思いを優先させたい。

ジャーナリスト
元日本経済新聞編集委員
浅川 澄一
1971年、慶應義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)





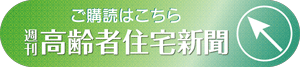

10.2-2-1.jpg)