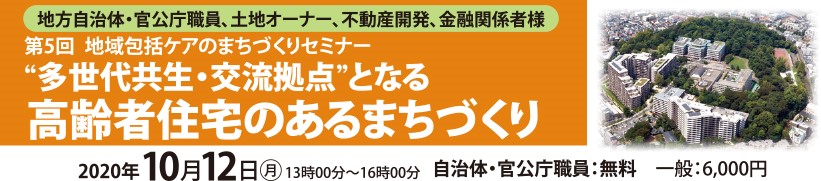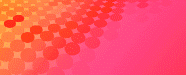著名人の死亡記事で「老衰死」が目立つ。10月10日にはユニ・チャームの創業者、高原慶一郎氏(87歳)が、翌11日には初代内閣安全保障室長の佐々淳行氏(87歳)が、そして22日にはノーベル化学賞受賞者の下村脩氏(90歳)が、いずれも「老衰のため死去」とあった。
厚労省の2017年の人口動態統計によると、老衰死は10万1306人に達した。老衰死はこの10年ほどの間に急増しており、17年には肺炎を抜いて死因の第4位に浮上。
だが、全死亡原因の中ではわずか8%弱しかない。実感よりだいぶ少ない。死亡統計を点検してみると大発見があった。
医師が記入する死亡診断書の死因欄はアイウエの4つの枠がある。(ア)には「直接死因」を、(イ)には「アの原因」を、(ウ)には「イの原因」を、(エ)には「ウの原因」をそれぞれ記入する。例えば、ア欄に急性呼吸不全、その原因としてイ欄に脳梗塞と書く。上の欄の原因がなければ以下は空欄でいい。厚労省作成の「死亡診断書マニュアル」では、死亡統計を作成する際には、「最下欄の病名を死因とする」とある。
しかし、最下欄に老衰と記入されている場合は、例外として、その上の欄の病名が死因となる。これでは、老衰の集計数が減ってしまう。老衰が死因として認められるのは、ア欄に老衰と書かれ、イ欄以下が空白の場合だけである。
さらに不思議なのは、「老衰から他の病態を併発した場合は、医学的因果関係に従って記入する」とあり、老衰のほかの病名を書くべきと指導している。その事例として、ア欄に誤嚥性肺炎、イ欄に老衰とある。
つまり、医師が「年齢からして老衰死だが、直接の死因は嚥下力が衰弱しての誤嚥性肺炎かな」と判断し、誤嚥性肺炎と書き込むと、死因統計では老衰でなくなってしまう。現場の医師からは「えっ、知らなかった」という声が聞かれる。同マニュアルには老衰の「最下欄外し」が書いてない。
老衰を排除し、死因統計から追い出そうという目論見だ。厚労省に問い合わせると「日本が準拠しているWHO(世界保健機構)の規則」と素っ気ない。では、WHOの考え方はどうなのか。
「疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD―10、2013年版)」には、「死亡防止の観点からは、疾病事象の連鎖をある時点で切るか、ある時点で疾病を治すことが重要。また、最も効果的な公衆衛生の目的は、その活動によって原因を防止すること」とある。
これで合点がいく。死因を調べる目的は、死亡を防ぐためなのだ。「老衰」が入るのは趣旨に合わない。WHOは、「保健」至上主義を掲げ、その理念からすると当然かもしれない。
先述の同マニュアルは「死亡統計は国民の保健・医療・福祉に関する行政の重要な基礎資料として役立つ」とその意義を高らかに宣言している。だが、WHOの価値観に引きずられ、死亡原因が歪められてしまった。
それでも、老衰死は年々急激に増えている。実は、がん、心疾患、脳血管疾患についても、「平均寿命以上の高齢者については、その死亡の遠因はほとんど老衰とみていい」と指摘する医師は少なくない。延命治療を断り「命が自然に閉じる」老衰死への選択が相当に浸透しつつある。
ジャーナリスト
元日本経済新聞編集委員
浅川 澄一
1971年、慶應義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow @kj_shimbun





10.2-2-1.jpg)

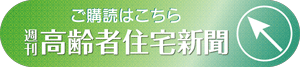

10.2-2-1.jpg)