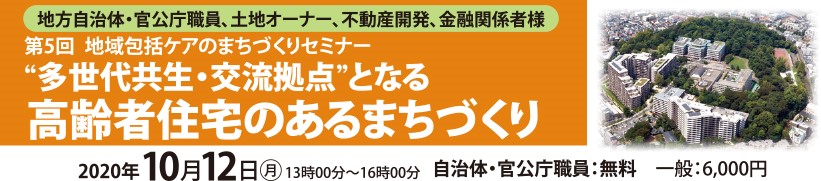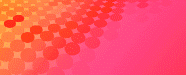---連載 点検介護保険---
昨年6月に政府が決めた認知症施策推進大綱と近々施行される認知症基本法で「予防」が強調された。これに反対する認知症の当事者団体は「予防を取り消して、『備え』にして」と訴えている。「誰でも認知症になる可能性はある。認知症になっても普通の暮らしを続けられるように、『備え』で」と言う。その通りだろう。
なぜ、「予防」が前面に出てきたのか。それは、認知症が病気であるとみなし、病気なら予防できるとなったのだろう。だが、本当に認知症は病なのだろうか。
認知症になる人を年齢別にみると、60代後半ではわずか2・9%だが、70代後半では13.6%に増え、80代後半になると41.4%と半数近い。そして95歳以上では79.5%と5人のうち4人だ。
つまり年齢が上がるとともに増えていく。一昨年の女性の平均寿命が87.3歳であるから、その年齢の半数近い高齢者が認知症ということになる。これほど多くの人が、同じ病気にかかることに疑問が湧くはず。
加齢と歩調を合わせて増加するということは、実は、老化、老衰によって現れる症状と見た方がいいだろう。
「病気」としたいのは医療の人たちである。医療が着目するのは個別臓器であり、その病名。自然の老いや生活は関心外だ。
認知症ケアの歴史を振り返れば、医療の介入から徐々に離れて、「生活ケア」に近づく流れであったことは明らかだ。「認知症ケアの切り札」と言われたグループホームは医療保険でなく、介護保険の中で制度化された。
グループホームは、家庭的環境を求められ、自宅にいる時と同様の暮らしが続けられる。画像診断では、脳細胞の機能不全が著しいため、「とても日常生活が難しい。入院しては」と医師から判定される高齢者でも、グループホームでは極めて穏やかに暮らす事例は多い。
グループホームに入居しなくても、家族や地域住民の暖かい声掛けや手助け、そして介護保険の在宅サービスを活用すれば、自宅生活を続けられる。地域のコーラスやカラオケ、ヨガなどのサークルに通うことで、一律な画像診断に勝る活力が生み出されることもよく聞く。
もし、病気であれば、その症状は誰でも同様に現れるだろう。だが、認知症では心身の動きは従来通りにはいかなくても、周囲の対応によってほとんど不自由を感じない暮らしができる。これを、病気とくくるのはおかしい。

医師の中でも病気説に反論する声が上がっている。東京大学名誉教授の大井玄医師は「認知症は、長生きすれば誰にでも起こる正常な現象です」「長生きに伴う心身の『障害』であって、『病気』ではない」と語っている。
「沖縄や離島、あるいはベトナムなどでは、周辺症状が出現しない認知症の方が多い」と話す。「高齢者が尊敬され、高齢者自身も誇りを持ち続けられる生活環境であれば問題が起こりにくい。慣れ親しんだ世界と断ち切られると、普通の人でも不安な状態になってしまう」。
大井さんが、病気説に疑問を抱き始めたのは、松下正明医師の講演を聞いた時だという。東京都健康長寿医療センターの元理事長で東京大学名誉教授の松下医師は「アルツハイマー型認知症は、脳の病気ではなく、脳の老化現象の促進された状態である」と主張している。
47年前に小説「恍惚の人」が出版され、その後、映画や演劇になって、認知症(当時は痴呆症)が多くの日本人に知られることになった。その中で描かれた本人は「人格欠損の人」であり、「同居困難になれば精神病院に収容」とされた。
小説は認知症の義父の世話にあたる女性の視点から綴られる。「何も分からなくなった困った人」という受けとめ方が、読者や観客の間に定着してしまう。当時の医療界の限界でもあった。
それが、「病気」の人と診断され、家族の気持ちは大きく変わったと言われる。
確かに、認知症はその原因が単純ではない。それにより対応法も変わり、他の病気を伴う可能性があるので診療は必要だろう。
だが、基本は老化であり、全身の細胞が機能を弱めて死に向かう過程で起きる脳の「障害」と見ていいだろう。
浅川 澄一 氏
ジャーナリスト 元日本経済新聞編集委員
1971年、慶応義塾大学経済学部卒業後に、日本経済新聞社に入社。流通企業、サービス産業、ファッションビジネスなどを担当。1987年11月に「日経トレンディ」を創刊、初代編集長。1998年から編集委員。主な著書に「あなたが始めるケア付き住宅―新制度を活用したニュー介護ビジネス」(雲母書房)、「これこそ欲しい介護サービス」(日本経済新聞社)などがある。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow @kj_shimbun

10.2-2-1.jpg)





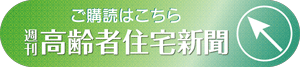

10.2-2-1.jpg)